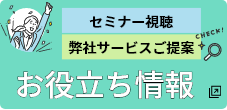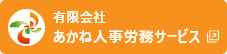【緊急解説】退職代行が増えている今、企業に求められる適切な対応とは?
2025.07.24
労務コラム
今回は、近年ますます注目を集めている「退職代行サービス」について取り上げます。
特に若年層を中心に利用が広がっているこのサービス。
ある日突然、従業員の代わりに退職の連絡が外部から届く──
そんなケースが増えてきており、企業の皆様も「どう対応すればいいのか」とお困りの場面があるのではないでしょうか。
退職代行サービスの仕組みや法的な考え方、企業として取るべき適切な対応方法、そして今からできる予防策について、やさしくわかりやすく解説いたします。
________________________________________
■ そもそも「退職代行」とは?
退職代行サービスとは、労働者が自ら会社に退職を伝えず、第三者(退職代行業者)を通じて退職の意思を伝えたり、手続きを進めたりするものです。
心理的なストレスやパワハラへの懸念、過去の引き留め経験などが原因で、「直接言いにくいから…」と、こうしたサービスを利用する人が増えています。
退職代行には大きく分けて3つのタイプがあります。
① 弁護士による退職代行
退職意思の伝達だけでなく、未払い賃金や残業代、損害賠償などの請求・交渉も法的に認められています。
② 一般の退職代行業者(弁護士資格なし)
あくまで「退職の意思を伝える」ことのみが許されており、会社との交渉(有給の取り扱いや未払い賃金など)は行えません。
③労働組合(ユニオン)による退職代行
労働組合法により、会社との交渉権限を持っていますが、ハラスメント被害の請求など一部対応できない内容もあります。
このように、「どのタイプの業者なのか」によって、企業としての対応も変わってくるため、見極めが大切です。
________________________________________
■ 突然、退職代行から連絡が来たら?
企業にとって、退職代行からの連絡は予期せぬ出来事です。
「本日から出社しません」「退職日までは有給を使います」「連絡はすべて代行業者に」──
こうした内容がメールや電話で届くこともあります。
まず押さえておきたいのが、労働者には「退職の自由」があるということ。
民法第627条では、期間の定めがない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間後には雇用関係が終了すると定められています。
つまり、企業側が「引き留めたい」と思っても、法的にはそれを強制することはできません。
とはいえ、突然の退職により現場に混乱が生じたり、他の社員への負担が増えたりするのも事実。
最悪の場合、退職が連鎖するリスクもあるため、できるだけ早く冷静に対応することが重要です。
________________________________________
■ 企業としての適切な対応ステップ
退職代行への対応にあたっては、次のような流れで対応するとスムーズです。
①退職代行が本人からの依頼であるか、事実を確認する
退職代行業者が本当に従業員本人の依頼で連絡しているのか、必ず確認しましょう。また、いやがらせ等の可能性も考慮し、慎重に対応し、退職届の提出を依頼しましょう。ハラスメントなどが背景にある場合もあるので、「一方的に退職するな」と責めるのではなく、丁寧に状況を確認する姿勢が大切です。
② 業者の種類を確認する
連絡してきた退職代行業者が「弁護士」「一般業者」「ユニオン」のいずれなのかを確認し、委任状などの提示を求めましょう。業者の種類によって、どこまで話し合いができるかが大きく異なります。
③ 必要な退職手続きを進める
退職届出の内容に不備がないか確認した後、必要な退職手続き(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など)の準備を進めましょう。
また、会社から貸与している物品等があれば、返却を依頼しましょう。
従業員が退職した場合、請求があれば賃金を支払う義務があり、給与や退職金の支払いについては、労働基準法第23条により、請求があった場合は原則7日以内に支払う必要があります。退職金は同条には該当しませんが、就業規則や退職金規程に則り、支払時期や算出方法を明確にしておくことが重要です。
また、労働者から証明書(職務内容・地位など)の交付を求められた場合には、速やかに対応しましょう(労基法第22条)。
________________________________________
■ 退職代行を防ぐには? 企業ができること
退職代行を利用される背景には、職場環境や人間関係への不安があるケースが多いといわれています。そこで、日頃から以下のような労務管理の取り組みが効果的です。
● 発言しやすい職場づくり
パワハラや過重労働があると、従業員は声を上げづらくなります。
日常的に「困ったことがあれば相談できる」雰囲気づくりを意識しましょう。
● 1on1ミーティングやメンター制度の導入
若手社員や中途入社社員が孤立しないよう、定期的な面談や相談相手を確保する仕組みづくりが有効です。
● ハラスメント対策と就業規則の整備
ハラスメントの有無は従業員の離職に直結します。また、退職に関するルールが曖昧なままではトラブルのもとになりかねません。就業規則は必ず見直しておきましょう。
● 専門家による診断・アドバイスを活用
外部の専門家(社労士)による労務監査や相談体制を整えることで、職場の問題点に早期に気づき、適切な対策を講じることができます。
________________________________________
■ 最後に:働く人も、企業も大切にする労務管理を
退職代行サービスの普及は、働く人々のニーズや社会の変化を反映しているともいえます。
しかし、企業としては突然の人員減少や手続き負担、職場の士気低下など、さまざまな影響が避けられません。
だからこそ、普段からの丁寧な労務管理や職場環境づくりがカギになります。
もし「自社の体制に不安がある」「退職代行対応の経験がない」といったことがあれば、どうぞ遠慮なく専門家弊社にご相談ください。
私たちは、企業と従業員がともに安心して働ける環境づくりを全力でサポートいたします!
★問い合わせフォーム
お問い合わせ | あかね社会保険労務士法人 お気軽にご連絡くださいませ。