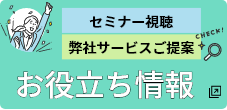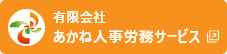【働き方の多様化】社員の副業・兼業、貴社はもう対応済みですか?企業に求められる対策と留意点とは?
2025.10.07
労務コラム
こんにちは。
あかね社会保険労務士法人です。
最近では「収入を増やしたい」「スキルアップしたい」「新しい挑戦をしてみたい」などの理由から、副業・兼業を希望する社員がどんどん増えています。政府もガイドラインを改定し、企業としてどのように対応していくべきかを示しています。
では、貴社では社員の副業・兼業についてルールを整えていますか?
「これまで認めていなかったから」「何から始めていいかわからない」などの理由で対応が遅れると、思わぬトラブルや優秀な人材の流出につながる可能性もあります。
厚生労働省のガイドラインやモデル就業規則をもとに、企業が取り組むべき副業・兼業への対策やポイントをわかりやすく整理しました。
________________________________________
1. なぜ今、副業・兼業への対応が重要なのか?
裁判例では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」とされており、企業が副業・兼業を全面的に禁止することは難しいのが実情です。
むしろ、副業・兼業を認めることには、企業側にも多くのメリットがあります。
• 人材育成:社員が社内では得られない知識やスキルを獲得できる。
• 競争力向上:社員の自律性・自主性を促し、優秀な人材の獲得・流出防止につながる。
• 事業機会の拡大:社員が社外から新たな情報や人脈を得ることで、オープンイノベーションが促進される。
一方で、企業としては「労務提供上の支障」「情報漏洩」「長時間労働による健康問題」といった懸念点があるのも事実です。だからこそ、ルールを明確に定め、適切に運用することが不可欠なのです。
________________________________________
2. 企業が取るべき具体的な対策・留意点
【対策1】就業規則の見直し・整備
まずは、就業規則に副業・兼業に関する規定を設けることが第一歩です。厚生労働省のモデル就業規則でも、副業・兼業に関する条項が設けられています。
◆ 原則容認と届出制の導入 就業規則では、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが適当です。その上で、会社が労働者の副業・兼業の状況を把握し、適切に管理するために「届出制」を導入することが望ましいとされています。
◆ 禁止・制限が可能なケースを明記 無条件にすべてを認めるのではなく、裁判例で示されている以下のケースに該当する場合には、禁止または制限できる旨を具体的に規定しておくことが重要です。
① 労務提供上の支障がある場合:長時間労働による健康状態の悪化や、本業への集中力低下が懸念されるケース。
② 企業秘密が漏洩する場合。
③ 競業により、企業の利益を害する場合。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合。
これらの規定を就業規則に設けることで、企業はリスクを管理しつつ、労働者の多様な働き方を支援する姿勢を示すことができます。
【対策2】労働時間の通算管理
労働者が雇用される形で副業・兼業を行う場合、労働基準法第38条第1項に基づき、自社と副業・兼業先の労働時間を通算して管理する必要があります。これは、事業主が異なる場合も同様です。
◆ 原則的な労働時間管理の方法
通算管理は、以下の順序で行うのが原則です。
1. 所定労働時間の通算:先に労働契約を締結した企業の所定労働時間から順に通算する。
2. 所定外労働時間の通算:実際に労働が行われた順に通算する。
この通算の結果、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える部分は時間外労働となり、後から契約した企業や、実際に法定労働時間を超える労働をさせた企業に割増賃金の支払義務が発生します。
◆ 簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)の活用
上記の原則的な管理は、特に所定外労働が発生した場合に複雑になりがちです。そこで、ガイドラインでは「管理モデル」という簡便な方法が示されています。
これは、副業・兼業の開始前に、「自社での法定外労働時間の上限」と「副業・兼業先での労働時間の上限」をあらかじめ設定し、その範囲内で各社が労働時間を管理する手法です。これにより、他社の実労働時間を都度把握する負担が軽減されます。多くの導入企業では、副業・兼業先での労働時間上限を月20~35時間程度で設定しています。
【対策3】労働者の健康管理
副業・兼業で最も懸念されるのが、長時間労働による健康障害です。企業には安全配慮義務があり、労働者の健康状態を適切に管理する責任があります。
• 労働者とのコミュニケーション:副業・兼業の状況を定期的に報告させ、健康状態に問題がないか確認する体制を整えましょう。心身の不調があれば相談できる窓口を設けることも有効です。
• 自己管理の促進:労働者自身が就業時間や健康状態を管理する必要があるため、その重要性を伝え、自己管理を行うよう促すことが求められます。
• 長時間労働者への面接指導等:副業・兼業先の労働時間を直接通算して実施義務を判断するわけではありませんが、自社の労働時間と合わせて長時間労働が認められる労働者には、申出により医師による面接指導を行うなど、法定の健康確保措置を確実に実施する必要があります。
________________________________________
まとめ:適切なルール作りが企業の未来を守る
副業・兼業は、もはや一部の特別な働き方ではありません。企業がこの変化に対応するためには、「就業規則の整備」「労働時間管理の徹底」「健康管理への配慮」という3つの柱が不可欠です。
これらの対策を怠ると、未払い割増賃金の発生や、安全配慮義務違反による損害賠償請求といった労務リスクに直面する可能性があります。
「自社の就業規則は今のままでいいのだろうか?」
「管理モデルを導入したいけれど、どう進めればいいか分からない」
「社員から副業の申請があったらどう対応すればいいのか迷っている」
そんなお悩みはありませんか?
最新の法改正やガイドラインに沿った就業規則改定のサポートから、日々の労務相談、勤怠管理のアドバイスまで幅広く対応しています。
副業・兼業制度を安心して導入・運用できるよう、まずはお気軽にご相談ください。
★問い合わせフォーム
お問い合わせ | あかね社会保険労務士法人 お気軽にご連絡くださいませ。