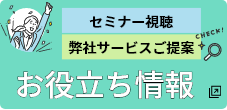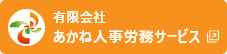仕事と育児・介護の両立を支援するテレワークの適切な導入・運用ガイド!
2025.10.15
労務コラム
こんにちは。
あかね社会保険労務士法人です。
今回は「テレワーク」をテーマにお届けします。
コロナ禍をきっかけに一気に広がったテレワークですが、今や働き方改革やDXの流れにのり、多くの企業で欠かせない制度となりました。特に育児や介護と両立するうえで、ますます重要性が高まっています。
2025年4月から改正育児・介護休業法の一部が施行され、テレワーク導入に関する新しい努力義務・義務が加わったのも記憶に新しいですよね。
「自社の制度はこのままで大丈夫かな?」と感じられる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法改正のポイント・制度を適切に運用するための労務管理上の留意点をまとめました。
________________________________________
1. 改正育児・介護休業法とテレワークの位置づけ
2025年4月1日から段階的に施行されている改正育児・介護休業法では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会を目指し、柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されました。
【改正のポイント】
• 育児・介護のためのテレワーク導入(努力義務):
◦ 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講じることが努力義務化されました。
◦ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講じることが努力義務化されました。
• 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への措置(義務):
◦ 事業主は、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇の付与、⑤短時間勤務制度の中から、2つ以上の措置を選択して講じる義務があります。労働者はその中から1つを選択して利用できます。
• 3歳未満の子の短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加:
◦ 短時間勤務制度の導入が困難な業務に従事する労働者がいる場合、労使協定を締結すれば代替措置を講じることができますが、その選択肢にテレワークが追加されました。
これらの改正により、テレワークは育児・介護を行う労働者のための重要な選択肢として法的に位置づけられました。企業は就業規則等を見直し、これらの措置に対応できる体制を整える必要があります。
________________________________________
2. テレワーク導入・運用のための労務管理上の留意点
厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づき、労使双方にとって有益な「良質なテレワーク」を実現するためのポイントを解説します。
(1) ルールの策定と周知
テレワークを円滑に導入・実施するには、あらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが不可欠です。
• 就業規則への規定: 導入目的、対象者、対象業務、費用負担、労働時間管理の方法、中抜け時間の取扱いなどを就業規則に明記し、労働者に周知することが望ましいです。特に、労働者に費用負担をさせる場合は就業規則への規定が必須です。
• 労働条件の明示: 労働契約締結時に、テレワークを行う場所(自宅、サテライトオフィス等)を「就業の場所」として明示する必要があります。
(2) 対象者と対象業務の適切な選定
• 対象者: 正規・非正規といった雇用形態の違いのみを理由に対象者から除外することはできません。新入社員や異動直後の社員など、コミュニケーションに不安がある従業員には特に配慮が必要です。
• 対象業務: 「テレワークに向かない」と安易に結論づけず、業務プロセスの見直し(ペーパーレス化、決裁の電子化など)を検討することが望ましいです。
(3) 労働時間管理の工夫
テレワークでは労働時間の把握に工夫が必要ですが、情報通信技術の活用で円滑な管理が可能です。
• 労働時間の把握:
◦ 原則は客観的な記録: PCの使用時間の記録など客観的な記録を基礎とすることが原則です。
◦ 自己申告制の場合: やむを得ず自己申告制とする場合は、労働者への十分な説明、実態との乖離がないかの確認、適正な申告を阻害する措置(上限設定など)の禁止といった措置が必要です。
• 長時間労働対策: 仕事と生活の区別が曖昧になりがちなため、長時間労働を防ぐ対策が重要です。
◦ 時間外のメール送付抑制やシステムへのアクセス制限。
◦ 時間外労働の事前許可制の導入。
◦ 長時間労働者への注意喚起。
• 中抜け時間: 業務から離れる「中抜け時間」は、休憩時間として終業時刻を繰り下げる、あるいは把握せずに始業・終業時刻間の時間を労働時間とみなす等の取扱いが考えられます。いずれの場合も、あらかじめ就業規則で定めておくことが重要です。
(4) 人事評価、費用負担
• 人事評価: 非対面での勤務実態を公平に評価するため、成果やプロセス評価の基準を明確化し、評価者への研修を行うことが望ましいです。時間外のメール等に対応しなかったことを理由とする不利益な評価や、オフィス出勤者を高く評価することは不適切です。
• 費用負担: 通信費や光熱費など、テレワークで生じる費用負担については、労使で十分に話し合い、就業規則等でルールを定めておくことが望ましいです。
(5) 安全衛生の確保
テレワークでも労働安全衛生法は適用されます。事業者は労働者の安全と健康を確保する措置を講じる義務があります。
• 作業環境整備: 自宅での作業環境が適切か、チェックリストを用いて労働者自身に確認させ、問題があれば労使で協力して改善を図ることが重要です。
• メンタルヘルス対策: コミュニケーション不足による孤独や不安に対応するため、健康相談体制の整備や定期的なオンライン面談の実施が望ましいです。
• 労働災害: 業務に起因する災害は労災保険の対象となります。この点を従業員に周知し、災害発生状況を記録しておくよう指導することが望ましいです。
________________________________________
3. まとめ:就業規則の見直しと労務管理体制の整備を
今回の法改正を機に、テレワークは単なるBCP対策や福利厚生の一環ではなく、多様な人材が活躍し続けるための重要な経営戦略として位置づける必要があります。
貴社では、
• 育児・介護を行う従業員が利用しやすいテレワーク規程になっていますか?
• 労働時間管理や評価制度は、テレワークの実態に合っていますか?
• 従業員の安全と健康を守る体制は十分に整っていますか?
テレワークは「福利厚生のひとつ」から「経営戦略の一部」へと位置づけを変えています。
制度や運用ルールを整えることは、従業員が安心して長く働ける環境づくりにつながります。
あかね社会保険労務士法人では、
• テレワーク勤務規程の改定サポート
• 運用に関する労務相談 を承っております。
「うちの制度はこのままで良いのかな?」といった小さな疑問からでも大歓迎です。
お気軽にご相談ください。
★問い合わせフォーム
お問い合わせ | あかね社会保険労務士法人 お気軽にご連絡くださいませ。