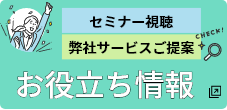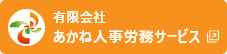【5月病×ハラスメント】 ―社員の“沈黙”を見逃さない。今こそ見直す職場のメンタルヘルスと労務リスク対策―
2025.05.16
労務コラム
こんにちは。あかね社会保険労務士法人です。
新年度が始まり、環境が大きく変わる春。新入社員の入社や人事異動、体制変更など、多くの企業で変化があったのではないでしょうか。そんな緊張感のある4月を乗り越えた後、5月は「少し落ち着いた」と感じる一方で、メンタル不調や職場の人間関係の“ゆがみ”が表面化しやすいタイミングでもあります。
特にこの時期に注意したいのが、「5月病」と「職場のハラスメント」です。
社員が知らず知らずのうちに不調を抱え込んでしまったり、ハラスメントが水面下で進行していたりと、放置すれば重大な労務トラブルに発展しかねない問題が起こりやすくなります。
■ 5月病とは?企業として知っておきたい基礎知識
「5月病」とは正式な病名ではありませんが、新しい環境や人間関係に適応しきれず、心身に不調をきたす状態を指します。主に新入社員や異動した社員、管理職に昇進した社員に多く見られますが、ベテラン社員にも起こり得る問題です。
【5月病によくある症状】
- 朝起きられない、出社がつらい
- 頭痛や胃痛などの体調不良が続く
- 感情が不安定でイライラしやすい
- 仕事へのモチベーションが上がらない
- 遅刻や欠勤が増える、突然の退職意思表示
特に厄介なのは、こうしたサインが最初は目立たないことです。結果として周囲が気づかないまま状態が悪化し、長期休職や退職につながるケースも少なくありません。
■ 5月病と職場ハラスメントには「意外な関係」がある?
さらに、私たち社労士が現場で多く見てきたのが、「5月病」と「ハラスメント」がセットになって現れるケースです。
【実際にあった労務相談事例】
- 上司からの強い指導が、部下にとってパワハラと感じられ、不調の原因に
- 出産・育児から復帰した女性社員が職場で孤立し、マタハラの相談へ発展
- 同期社員同士のトラブルが上司に共有されず、長期の不調につながった
これらは「グレーゾーン」の問題が多く、就業規則に記載があっても、現実の現場で対応に迷うケースがほとんどです。
そして、このようなトラブルは、放置すれば企業としての責任を問われる事態(損害賠償・評判リスク)につながりかねません。
■ 今こそ必要な“見直し”と“備え”
5月は、忙しい4月がひと段落した今だからこそ、以下の2つの視点で労務体制を見直す絶好のタイミングです。
① 社員の変化に気づく体制を整えること
- 定期的な1on1や面談を行い、心の変化を見逃さない
- 部下の様子に気を配る「管理職研修」も有効
- 社内相談窓口の存在を周知・活用を促す
② ハラスメント対策を「形だけ」にしないこと
- 就業規則の内容が現状に合っているか見直す
- 実践的な研修や、相談対応マニュアルを整備する
- 外部専門家(社労士)の力を借りて、第三者視点を取り入れる
これらの整備ができていないと、「問題が起きてから」あわてて対応することになり、結果として信頼やコストの損失に直結してしまいます。
■ 社労士がサポートできること
あかね社会保険労務士法人では、日常の労務相談をはじめ、就業規則の整備や社内研修、ハラスメント対応支援、そしてメンタル不調の早期発見のサポートまで、幅広い企業支援を行っております。
私たちが重視しているのは、単なる「相談窓口」ではなく、“社員の変化に気づき、予防的に動く”体制づくりです。
労務問題は、相談のタイミングや初動の対応で結果が大きく変わります。社内だけで判断せず、**「第三者に相談できる安心感」**を持っていただくことが、結果としてトラブルの予防につながります。
■ まとめ:今こそ、整備と対話の「一歩」を
新年度の波が落ち着く5月だからこそ、あらためて職場のメンタルヘルスやハラスメントの備えを点検する絶好のタイミングです。
- 社員が“沈黙”していないか
- 上司や人事担当者が、対応に迷っていないか
- 労務リスクを未然に防げる体制になっているか
「ちょっと気になることがある」「一度、外部の目で見てもらいたい」
そんな時は、是非弊社までご相談ください。随時、労務顧問契約に関するご相談も承っております。お問い合わせ | あかね社会保険労務士法人 お気軽にご連絡くださいませ。