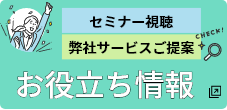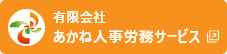常時50人を超えたら――労働安全衛生法で“必ず”整えることとは?
2025.09.17
労務コラム
従業員数が50人を超えると、会社に求められる労務管理のルールが一段階アップするのをご存じでしょうか?
最近は顧問先様からも「具体的に何を整えればいいのか知りたい」というご相談をよくいただきます。
そこで今回は、労働安全衛生法に関連する実務対応ポイントをわかりやすく整理しました。これから規模拡大を見込まれている企業様にも、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
常時50人を超えたら――労働安全衛生法で“必ず”整えること
1.体制整備:産業医・衛生管理者・衛生委員会
最初の一歩は体制の確立です。常時50人以上になったら、産業医と衛生管理者を速やかに選任し、所轄労働基準監督署へ届出します(目安:選任事由発生後14日以内)。併せて、衛生委員会を毎月1回以上開催できる運用に乗せ、議事概要の周知と議事録3年保存を徹底します。委員会は「決める場」。労働時間の分布、長時間労働者の面接指導実施状況、健診の有所見率、休業災害・ヒヤリハットの傾向など、職場データを基に、対応方針・期限・責任者を明確化すると運用が安定します。産業医には、職場巡視や面談、就業上の措置に関する助言まで役割を具体化し、委員会でフォローすると効果的です。
2.測定と報告:ストレスチェック・定期健診
ストレスチェックは年1回の実施が必要です。本人への結果通知と、医師による面接指導につながる導線(申出様式、予約方法、個人情報の取扱い)を明確にし、結果報告書の提出を忘れないこと。定期健康診断も同様に、結果評価→就業上の措置→再検・フォローまでを一連の運用に組み込み、委員会で進捗管理します。検査は「受けて終わり」ではなく、職場改善の起点として位置づけるのが要点です。
3.設備整備:休養室(休養所)
常時50人以上(または女性30人以上)の事業場では、臥床できる休養室(または休養所)の設置が求められます。男女の区別とプライバシー配慮がポイント。専用室が理想ですが、スペース制約がある場合でも、簡易ベッド・パーティション・入室管理等で機能を確保できます。利用対象や最大使用時間、緊急時の対応、清掃・衛生管理のルールは委員会で審議し、社内に周知しましょう。
4.業種により追加:安全管理者・安全委員会
製造・建設・運送等の特定業種は、規模区分に応じて安全管理者の選任や安全委員会の設置が必要になります。自社の産業分類と事業場規模を確認し、該当する場合は衛生体制と一体で設計するのが効率的です(衛生委員会と統合して安全衛生委員会とする運用も可能)。
5.つまずきやすい論点
✓人数のカウント:常時使用する労働者の捉え方や、派遣先で就労する派遣労働者の取り扱いに注意。
✓委員会の形骸化:KPI(有所見率、面接指導実施率、災害是正率など)と決定事項(期限・責任者)を明文化。
✓健康情報の保護:人事情報と健康管理情報のアクセス権限を分け、最小限の共有とする。
6.進め方の定石
①体制図(産業医・衛生管理者・委員構成・連絡系統)を確定 → ②年間カレンダー(委員会、健診、ストレスチェック、報告期限)を策定 → ③規程・様式(実施規程、面接申出書、議事録様式、個人情報取扱い)整備 → ④休養室の整備と運用ルール決定 → ⑤記録の一元管理(議事録、巡視記録、面談記録、提出控) → ⑥教育・周知(管理職研修・新入社員教育・相談窓口の明示)――この順で着手すると、初動の抜け漏れを抑えやすくなります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
「これから50人を超えそう」「もうすでに対象だけれど対応に不安がある」という企業様は、ぜひ今回のまとめをご活用ください。
さらに詳しい内容を整理したリーフレットもこちらからダウンロードいただけます。併せてご活用ください!
https://akanejinjiroumu.noco.sale/share/d/01K58M3EVM0AYMHFA2732CYTHB
あかね社会保険労務士法人
★問い合わせフォーム
お問い合わせ | あかね社会保険労務士法人 お気軽にご連絡くださいませ。